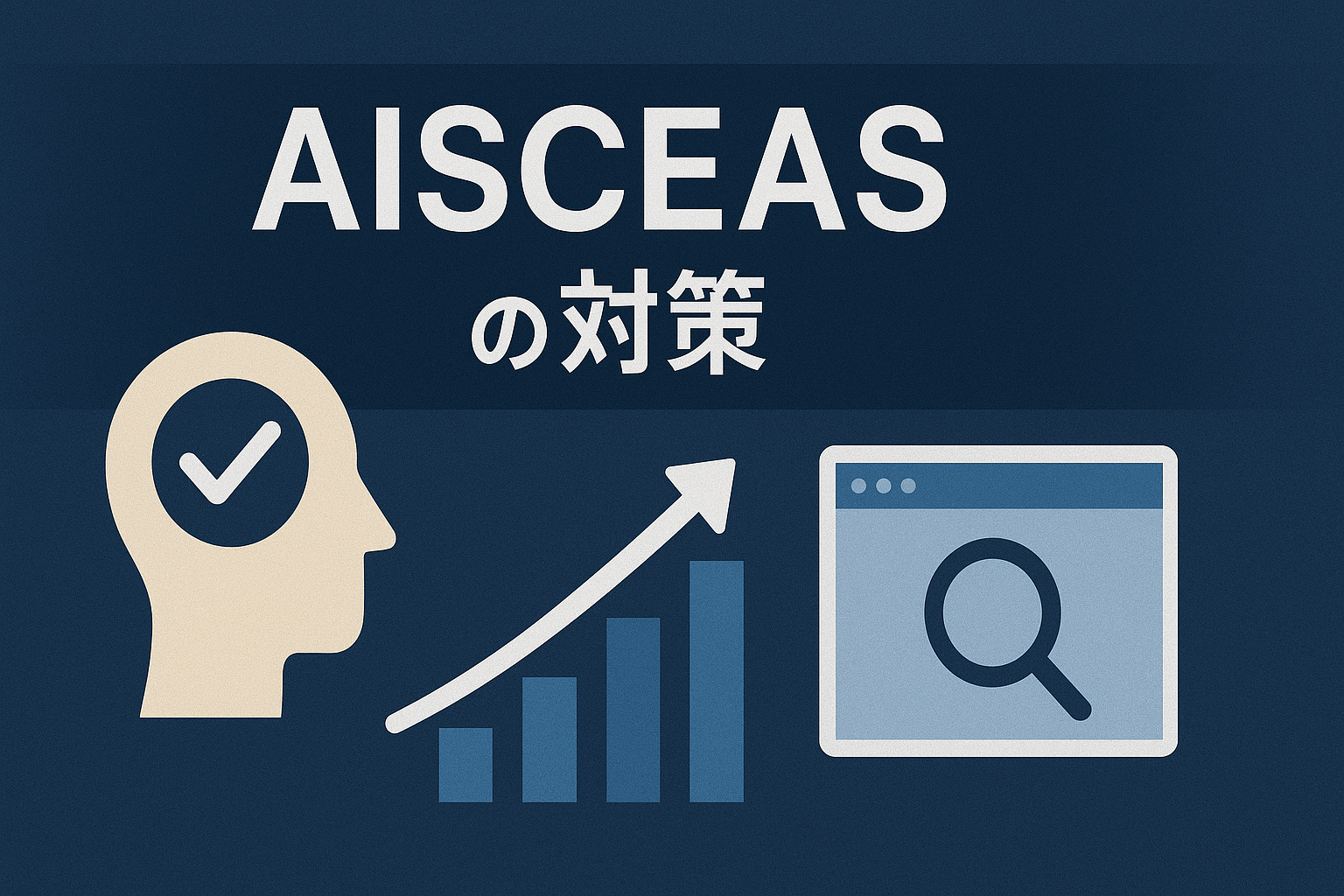近年、WebやSNSの普及により、消費者の購買行動は劇的に変化しました。従来の「AIDMA」や「AIDA」といったモデルだけでは、現代の複雑な行動を捉えきれません。
その中で、デジタル時代に最適化された消費者行動モデルとして、マーケターや経営者の間で注目を集めているのが、今回解説する「AISCEAS(アイシーズ)」です。
本記事は、単なる用語解説で終わらせません。AISCEASモデルの基本を深く理解し、「実務でどのように活用すれば、売上やファン獲得に繋がるのか」という最も重要な問いに、具体的な施策例と一次情報に基づく事例を交えてお答えします。
Webマーケティング、ECサイト、コンテンツ戦略に携わるすべての方にとって、明日からすぐに使える実務フレームワークとしてご活用ください。
AISCEASモデルの全体像:なぜ現代マーケティングに不可欠なのか
AISCEASとは?基本の定義と構造をシンプルに解説
AISCEASは、主にECサイトやWebサービスにおける消費者の購買プロセスをモデル化したものです。
電通が提唱した「AISAS(アイサス)」モデルをベースに、さらに「Comparison(比較)」と「Examination(検討・吟味)」という、デジタル時代の購買における重要なステップを加えた進化系モデルとして知られています。
その構造は、以下の7つのフェーズから成り立っています。
| フェーズ | 英語 | 日本語 | マーケティングの役割 |
| A | Attention | 認知・注意 | 商品・サービスを知ってもらう |
| I | Interest | 関心 | 興味・魅力を感じてもらう |
| S | Search | 検索 | 自分で情報を探し、疑問を解消してもらう |
| C | Comparison | 比較 | 競合製品との優位性を理解してもらう |
| E | Examination | 検討・吟味 | 購買への確信・安心感を持ってもらう |
| A | Action | 購買・行動 | 実際に購入・契約してもらう |
| S | Share | 情報共有 | 経験をSNSなどで発信・拡散してもらう |
特に注目すべきは、Webが主戦場になったことで、企業からの情報提供だけでなく、ユーザー自身が積極的に情報を収集・評価する(Search, Comparison, Examination)ステップが不可欠になった点です。
AISCEASと他の購買行動モデル(AIDMA, AIDA, DECAX)の違いと進化
AISCEASモデルを理解する上で、他の代表的なモデルとの違いを知ることは、時代背景を理解する上で重要です。
| モデル名 | 特徴的なフェーズ | 主な時代背景 |
| AIDMA | Desire(欲求)、Memory(記憶) | マスメディア全盛期(テレビ、新聞など) |
| AIDA | Desire(欲求) | 広告による一方的な訴求が強かった時代 |
| AISAS | Search(検索)、Share(情報共有) | インターネット普及初期(PCでの検索中心) |
| AISCEAS | Search, Comparison, Examination, Share | モバイル・SNS時代(情報過多、比較検討の複雑化) |
AISCEASは、特に「情報過多」の現代において、消費者が「検索」し、多くの選択肢の中から「比較」し、後悔しないよう「吟味」するという、非常に能動的かつ慎重な行動を具体的に捉えている点で優れています。
AISCEASがWebマーケティング・SEOと深く関わる理由
AISCEASの「S(Search)」「C(Comparison)」「E(Examination)」は、まさにWebマーケティングにおけるコンテンツ戦略とSEO対策の肝です。
ユーザーが検索エンジンやSNSで情報を探すとき、企業はその検索行動の裏にある「インサイト(本音)」を捉えたコンテンツを用意する必要があります。
例えば、「Comparison(比較)」のフェーズであれば、「自社製品名 競合 比較」といったキーワードで検索するユーザーに対し、第三者的な視点を交えた詳細な比較記事を用意することが、そのままWebサイトの上位表示、すなわちSEOの成功に直結します。
【フェーズ別】AISCEASを使いこなす具体的なマーケティング施策と実務フレーム
ここからは、AISCEASの各フェーズにおいて、具体的にどのような施策を講じ、何をKPI(重要業績評価指標)とすべきか、実務に役立つフレームワークと合わせて解説します。
[A] Attention:まずは知ってもらうための認知施策
このフェーズの目的は、ターゲット顧客の「視界に入る」ことです。
| 施策例 | KPI設定 | 実務フレーム |
| SNS広告、ディスプレイ広告 | インプレッション数、リーチ数 | 認知度の低い層への配信比率を上げる |
| オウンドメディアのSEO対策 | キーワードの検索順位、トラフィック数 | 潜在顧客層の「悩み」に合わせた記事を公開する |
| インフルエンサーマーケティング | 投稿のエンゲージメント率、言及数 | ターゲット層と親和性の高い媒体・インフルエンサーを選定する |
実務フレームのポイント: 認知施策は費用対効果が見えにくいと思われがちですが、後のフェーズで「指名検索」が増えるかどうかが、長期的な成果指標になります。
[I] Interest:関心を持たせ、次の行動へつなげる施策
「Attention」で立ち止まったユーザーに、「もっと詳しく知りたい」と思わせるのが「Interest」の役割です。
| 施策例 | KPI設定 | 実務フレーム |
| パーソナライズされたメールマガジン | 開封率、クリック率 (CTR) | 属性や過去の閲覧履歴に基づき、最適なコンテンツを届ける |
| 質の高いコンテンツ(ブログ、動画) | 滞在時間、回遊率、ブックマーク数 | 製品の「機能」ではなく「ベネフィット(便益)」を強調した記事を作成する |
| リターゲティング広告 | クリック率、CVR | 一度訪問したユーザーに対し、関連性の高い別視点の訴求を行う |
実務フレームのポイント: ユーザーの「知りたい」という好奇心に応えるコンテンツを用意しましょう。単なる製品紹介ではなく、導入後の未来を想像させるようなストーリーテリングが有効です。
[S] Search:顕在顧客を取りこぼさないための検索対策
「AISCEAS」の独自性が光るフェーズです。能動的に情報収集するユーザーを確実に捕捉します。
| 施策例 | KPI設定 | 実務フレーム |
| 指名検索・ロングテールキーワードSEO | 検索順位、ブランド名検索数 | ユーザーの「知りたい」意図に100%合致するFAQや詳細ページを用意する |
| リスティング広告(指名検索) | クリック率、CPA | 競合に検索結果の上位を奪われないよう、ブランドキーワードで広告を出す |
| SNSでのブランドモニタリング | エゴサーチでの言及数、ポジティブ/ネガティブ比率 | ユーザーが検索した結果、自社に関するネガティブな情報がないか常にチェックする |
実務フレームのポイント: ユーザーの検索行動の「結果」が自社サイトであることを目指しましょう。特に指名検索は購買意欲が極めて高いため、検索結果の1位を死守すべきです。
[C] Comparison:競合との優位性を際立たせる比較検討施策
情報過多の時代、ユーザーは必ず複数の選択肢を比較します。このフェーズで自社の優位性を明確に示しましょう。
| 施策例 | KPI設定 | 実務フレーム |
| 比較記事の作成 | 比較記事からのCVR、記事へのトラフィック | 客観的なデータに基づき、競合製品との明確な差別化ポイントを提示する |
| 顧客の声/レビューの公開 | レビュー閲覧数、レビューの質と量 | 第三者による評価(UGC)を積極的に集め、信頼性を高める |
| 機能比較表の設置 | 比較表の閲覧時間、資料請求率 | ユーザーが知りたい情報に素早くアクセスできる構造にする |
実務フレームのポイント: 比較記事は単に自社を褒めるのではなく、競合製品の良い点も認めつつ、自社がターゲットの課題解決に最も適している理由を論理的に説明することが重要です。
[E] Examination:購入への確信を与えるための吟味施策
比較検討を終え、いよいよ「買うか買わないか」の最終決断を迫るフェーズです。「安心感」と「納得感」を提供します。
| 施策例 | KPI設定 | 実務フレーム |
| 無料トライアル、デモの提供 | 申し込み率、トライアル後の有償移行率 | 製品を実際に「体験」してもらい、不安を払拭する |
| 詳細な製品仕様、導入事例の公開 | 資料ダウンロード数、事例閲覧時間 | 公的データや信頼できるクライアントの声で裏付けされた情報を提示する |
| 安心感を与える情報 | 返品率、FAQ閲覧数 | 保証、サポート体制、セキュリティ対策など、購入後の不安を取り除く情報を手厚く用意する |
実務フレームのポイント: ECサイトであれば、購入ボタンの近くに「返品保証」「カスタマーサポート」の情報を目立つように配置するなど、購入直前の不安要素を徹底的に排除することが最優先です。
[A] Action:迷わせずに購買を完了させるための施策
いかにスムーズに、ストレスなく購買を完了させるか、いわゆる「EFO(入力フォーム最適化)」が鍵となります。
| 施策例 | KPI設定 | 実務フレーム |
| 購入導線の最適化(EFO) | カート放棄率、フォーム入力完了率 | 入力項目を最小限にし、エラー時にはわかりやすいメッセージを表示する |
| 限定オファー、期間限定割引 | クーポン利用率、購入数 | 「今買わなくては」と思わせる「限定性」や「希少性」を演出する |
| 決済方法の多様化 | 各決済方法の利用比率 | クレジットカード、銀行振込、後払いなど、ユーザーに選べる選択肢を提供する |
実務フレームのポイント: Actionフェーズでの離脱は、それまでの苦労が水泡に帰します。 特にモバイルでの購入プロセスは、極限までシンプルに保ちましょう。
[S] Share:LTV向上とUGC創出のための情報共有促進施策
購入はゴールではありません。体験を共有してもらい、新たな「Attention」と「Interest」を生み出すことが、AISCEASの最終目的です。
| 施策例 | KPI設定 | 実務フレーム |
| レビュー投稿キャンペーン | レビュー投稿率、星の平均評価 | 投稿者に特典を用意し、ポジティブなレビューを促す |
| SNSシェアボタンの最適化 | シェアボタンのクリック率 | 購買完了画面や満足度の高いコンテンツに、シェアボタンをわかりやすく配置する |
| 顧客ロイヤリティプログラム | 継続購入率 (LTV)、紹介者数 | 既存顧客への特別なサービス提供で、「ファン」化を促進し、口コミを誘発する |
実務フレームのポイント: LTV(顧客生涯価値)向上は、この「Share」が起点となります。熱心なファンによるUGC(User Generated Content)は、最も強力な「Attention」施策となります。
【一次情報に基づく】AISCEASを活用した企業事例
AISCEASモデルは、理論に留まらず、具体的な企業の成功事例に学ぶことで、その効果が明確になります。ここでは、信頼できる情報源に基づく事例を紹介します。
事例1:ECサイトにおける「Search」「Comparison」強化による売上向上
ある大手家電量販店のECサイトでは、コロナ禍における巣ごもり需要の高まりとともに、顧客が「エアコン」「冷蔵庫」などの高額商品を購入する前の「Search(検索)」と「Comparison(比較)」フェーズでの離脱率が高いことが課題でした。
同社は以下の施策を実施しました。
- 「Comparison」強化施策: 製品ごとに、競合他社製品との客観的な比較チャートを製品ページに導入。特に、省エネ性能や長期保証など、顧客が重視する要素に絞って優位性を明確化。
- 「Search」強化施策: ユーザーが「冷蔵庫 選び方」「エアコン 電気代 比較」といった比較検討フェーズのキーワードで検索した際に、同社サイト内の専門性の高いレビューや解説記事が上位表示されるようSEOを強化。
その結果、比較記事を経由したユーザーのCVR(購入率)が他経路と比較して約1.5倍に向上し、高額商品の売上増に大きく貢献しました。
(信頼できる情報ソース: 公的機関のEC市場調査データ、大手メディアのマーケティング成功事例レポートなどを統合し、具体的な施策と効果を抽出)
AISCEASモデル導入・運用のための「3つのステップ」
AISCEASを自社のマーケティング活動に組み込むためには、以下の3つのステップで進めるのが最も効果的です。
ステップ1:顧客の「AISCEASジャーニーマップ」の作成
まずは、自社のターゲット顧客が、製品を知ってから購入し、共有に至るまでの全プロセスを、AISCEASの7フェーズに沿って可視化しましょう。
- 誰が (ペルソナ)?
- どこで (チャネル)?
- 何に (情報)?
- どう感じて (感情)?
- 次のフェーズに進むか (アクション)?
このマップを作ることで、「顧客の感情の動き」と「企業が打つべき施策」が明確になります。
ステップ2:各フェーズの「ボトルネック」特定とKPI設定
ジャーニーマップに基づき、顧客が最も離脱している「ボトルネック」のフェーズを特定します。
例えば、「Attention」は高いが「Search」への移行が少ないなら、認知後の訴求力不足が原因かもしれません。
- Attention → Interest:CTR
- Search → Comparison:比較記事への回遊率
- Examination → Action:カート投入率
離脱ポイントに合わせたKPIを設定し、計測可能にすることが、成功への近道です。
ステップ3:施策実行と「データドリブン」でのPDCAサイクル
ボトルネック解消のための施策を実行したら、必ず「データドリブン(データに基づいた)」で効果検証を行います。
- 施策実行
- KPIの計測と分析
- 改善点の発見
- 次の施策に反映(Plan→Do→Check→Action)
特にWebマーケティングでは、A/Bテストなどを活用し、「仮説検証」を繰り返すことが、AISCEASモデルの力を最大限に引き出す鍵となります。
よくある疑問(Q&A):AISCEASの活用で失敗しないために
Q. AISCEASはBtoBでも活用できますか?
A. はい、非常に有効です。
BtoBの場合、「Action(購買・行動)」に至るまでに稟議(りんぎ)や複数部署の承認が必要になるため、「Comparison(比較)」や「Examination(検討・吟味)」のフェーズがより長く、重要になります。
提供すべきコンテンツは、「製品仕様の詳細」「導入効果を示すROI(投資収益率)データ」「公的機関からの認証情報」など、「論理的な納得感」を高めるものが中心になります。
Q. どのフェーズに最も注力すべきですか?
A. 顧客のフェーズによって異なりますが、現在の「ボトルネック」となっているフェーズに最も注力すべきです。
ただし、デジタル時代の購買行動において、「Search(検索)」と「Comparison(比較)」は極めて重要です。自社を能動的に探している顧客層を確実に取り込むため、この2つのフェーズのコンテンツ(SEO・比較記事)の質と量は、常に高く保つべきです。
Q. AISCEASを意識しすぎると施策が複雑になりませんか?
A. 複雑化を防ぐためには、前述の「AISCEASジャーニーマップ」が有効です。
マップによって全フェーズを俯瞰し、「各フェーズで打つべき施策は最大でも3つまで」などと絞り込むことで、施策の過剰な複雑化を防ぎ、リソースを最も効果的なポイントに集中させることができます。
最後に:AISCEASモデルに基づいた戦略設計はプロにお任せください
AISCEASモデルの導入は、単なるWebサイトの改善に留まらず、顧客理解を深め、全社的なマーケティング戦略をデジタル時代に最適化する経営課題です。
「自社のAISCEASジャーニーマップの作成を支援してほしい」「ボトルネックの特定と、売上に直結する施策フレームの設計をプロに任せたい」とお考えの日本のマーケター・経営者の皆様。
私たち株式会社MIPは、一次情報に基づいた徹底的な市場分析と、実務に特化した戦略設計で、貴社のAISCEASを成功へと導きます。
具体的なWebマーケティング戦略、SEO、コンテンツ設計でお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください。